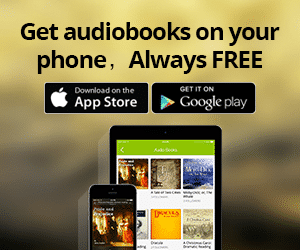ソウルにいた時と同様、東京でも行かない所がないくらいあらゆる土地を歩き回りました。友人が日光のような景勝地を見物に行くときも、私は一人残って東京市内の至る所を歩いて回ってみました。見た目はきらきらして華やかでも、東京の街もやはり貧者の天下でした。私は家から送金されたお金を皆、貧しい人々に分け与えました。
その時代は誰もがおなかを空かせていました。留学生の中にも苦学生が大勢いました。私は一カ月分の食券が手に入ると、全部持って行って彼らに渡して、「食べろ。思う存分食べろ」と言って、すべて使いました。自分ではお金の心配はしませんでした。どんな所でも働いて仕事をすれば、ご飯は食べることができたからです。お金を稼いで苦学生の学費を助けるのも私の楽しみでした。そうやって、人を助けたりご飯を食べさせたりすれば、体の奥からふつふつと力が沸いてきました。
所持金をはたいて全部分け与えた後は、リヤカーで荷物を配達する仕事をしました。東京の二十七の区域をリヤカーで縫うようにして回りました。電信柱を載せたリヤカーを引いて華やかな街灯がともる銀座を通った時、交差点の途中で信号が赤になってしまい、その場に立ち止まったため、道行く人々がびっくりして逃げていったこともあります。おかげで、今でも東京の隅々まで手に取るように分かります。
私は労働者の中の労働者であり、労働者の友達でした。汗のにおいと小便のにおいが漂う彼らと肩を並べて、私もまた作業現場に行って、汗を流して働きました。彼らは私の兄弟だったのであり、それゆえに、ひどいにおいも気になりませんでした。真っ黒なシラミが列をなして這っている汚い毛布も、彼らと一緒に使いました。何層にも垢がこびりついた手も、ためらわずに握りしめました。垢まみれの彼らが流す汗には粘っこい情けがあり、私はその情けが面白くて好きでした。
主に川崎鉄工所と造船所で肉体労働をしました。造船所には石炭運搬用の「バージ」と呼ばれる艀があって、ポンポン船がそれを曳航します。私は三人一組になって、午前一時までに石炭百二十トンをバージに積み込む仕事をしました。日本人が三日かけてする仕事を、韓国人は一晩でやってのけます。韓国人の手際のよさを見せてやろうと思い、無条件に一生懸命働きました。
作業現場には、労働者の血と汗を搾り取る輩がいます。労働者を直接管理する班長が往々にしてそうです。彼らは、労働者が汗水たらして稼いだお金の三割をピンはねして、私腹を肥やしていました。しかし、力のない労働者は全く抗議できませんでした。弱い者を苦しめ、強い者にへつらう人間。そんな班長に腹が立って我慢ならなかった私は、“三銃士”の友人を呼び集めて彼の元を訪ねていき、「仕事をさせたなら、させたとおりに金を払え!」と食ってかかったことがあります。一日で駄目なら、二日、三日としぶとく詰め寄りました。それでもまったく話を聞かないので、私の大きな体で足蹴りをして、班長を吹っ飛ばしてしまいました。私はもともと無口でおとなしい人間ですが、怒ると子供の頃の意地っ張りの気質が蘇り、蹴飛ばしてしまうこともよくやります。
川崎鉄工所には硫酸タンクがありました。労働者は硫酸タンクを清掃するために、タンクの中に直接入っていって原料を排出する仕事をします。硫酸はとても有毒で、タンクの中に十五分以上入っていることはできません。そんな劣悪な環境の中でも、彼らはご飯のために命がけで働きます。ご飯というものは、命とも引き換えにできるくらいに重要なものでした。
私はいつも空腹でしたが、いくらおなかが空いても、自分のために食べることはしませんでした。ご飯を食べるときには、はっきりした理由がなければならないと考えました。それで、食事のたびに、おなかが空いた理由を自らに問いただしてみました。「本当に血と汗を流して働いたのか。私のために働いたのか、それとも公的なことのために働いたのか」と尋ねてみました。ご飯を前にすることに、「おまえを食べて、きのうよりもっと輝いて、公的なことに取り組もう」と言うと、ご飯が私を見て、笑いながら喜んだのです。そんなときは、ご飯を食べる時間がとても神秘的で楽しい時間でした。そうでなければ、どんなにおなかが空いても食事をしなかったので、一日に二食食べる日もそれほど多くはありませんでした。
元から食べる量が少なくて一日二食で我慢したのではありません。若い盛りでしたから、私も食べ始めればきりがありませんでした。大きな器に盛ったうどんを十一杯まで食べたこともあり、また親子どんぶりを七杯食べたこともあります。それくらい食欲旺盛だったのに、昼食を抜いて一日に二食しか食べない習慣を三十過ぎまでかたくなに続けました。
おなかが空けば食べ物が恋しくなります。空腹時のご飯の恋しさは嫌というほど知っていますが、世界のためにご飯一食ぐらいは犠牲にできて当然だろうと思いました。新しい服を着てみたこともないし、どんなに寒くても部屋に火を入れませんでした。とても寒いときの一枚の新聞紙は、絹の布団のように暖かいものです。私は一枚の新聞紙の価値をよく知る男です。
ある時は品川の貧民窟で生活してみました。ぼろを被ったまま寝て、日差しの強い真昼になってシラミを捕まえたり、乞食たちがもらってきたご飯を分け合って食べたりしました。品川の通りには、流れ者の女性も大勢いました。一人一人事情を聞いてあげると、お酒を一口も飲めない私が、いつしか彼女たちのかけがえのない友になっていました。酒を飲まなければ本心を打ち明けられないというのは、空しい言い訳です。酒の力を借りなくても、彼女たちを不欄に思う私の心が真実だと分かると、彼女たちも素直な心で胸の内を明かしました。
日本で勉強する間、本当にありとあらゆることをしてみました。ビルの小使いや文字を書き写す筆生の仕事もしました。作業現場で働いて現場監督をしたこともあれば、人の運勢を占ったこともあります。生活に困れば、文字を書いて売ったりもしました。それでも、勉強をおろそかにはしませんでした。私は、そうしたことはすべて自分自身を鍛錬する過程だと考えました。いろいろな人に会ってみましたが、それを通して、人間をより多く知るようになりました。おかげで、人をちらっと見れば、「ああ、何をしている人だな」「この人は良い人だな」とすぐに分かります。頭であれこれ考える前に、体が先に分かってしまうのです。
私は今でも、人間が人格完成しようと思えば、三十歳になるまでは苦労してみなければならないと考えます。三十歳になるまでに、人生のどん底を這いずり回るような絶望の坩堝に一度ぐらいははまってみるべきでしょう。絶望の奈落の底で新しいものを探し出せというのです。そうすれば、「ははあ」と驚きの声を上げながら、「今の絶望がなければ、このような決心はできなかったはずだ」と心を新たにするようになります。絶望の淵から驚きの声を上げて抜け出してこそ、新しい歴史を創造する人に生まれ変わることができるのです。
一箇所だけ、一方向だけ見ていても大事は成せません。上も見て、下も見て、東西南北をすべて見なければなりません。人の生涯はどれも同じ七十年、八十年ではないのです。一度しかない人生であり、その間に成功できるか否かは、自分の目で物事を正しく見られるかどうかにかかっています。それには豊富な経験が物を言います。また厳しい環境にあっては、余裕のある人間味と柔軟な自主性が必ず必要です。
人格者は、一度上がって急降下する人生にも慣れていなければなりません。大抵の人は一度上がると、下がるのを恐れて、その地位を守ろうと汲々としますが、淀んだ水は腐るようになっています。上に上がったとしても、下に下りていって、時を待った後にさらに高い頂に向かって上がっていくことができてこそ、大勢の人から仰がれる偉大な人物、偉大な指導者になれるのです。三十歳になる前の若い時代に、こういったことをすべて経験しておくべきです。
ですから、私は今も青年たちに、世の中のあらゆることを経験してみなさいと勧めています。百科事典を最初から最後まで隈無く目を通すように、世の中のすべてのことを直接、間接に経験したとき、初めて自らの拠って立つ価値観が定まります。価値観とは何でしょうか。それは自らの明確な主体性です。「全国を見回してみても、私を負かす者はなく、私にかなう者はない」という自信を得た後に、最も自信のあるものを一つ選んで、一気に勝負をつけるのです。そうやって人生を生きれば必ず成功するし、成功せざるを得ません。東京で乞食の生活をしながら、私は以上のような結論に達しました。
私自身も、東京で労働者と寝食を共にしながら、また乞食と食うや食わずの悲哀を分かち合いながら、苦労の王様、苦労の哲学博士になってみて、初めて人類を救おうとする神の御旨を知ることができました。それゆえ、三十歳までに苦労の王様になることです。苦労の王様、苦労の哲学博士になること、それが天国の栄光に至る道です。
More Episodes
 2024-05-06
2024-05-06
 177
177
 2024-04-15
2024-04-15
 197
197
 2024-04-15
2024-04-15
 189
189
 2024-04-15
2024-04-15
 198
198
 2024-04-15
2024-04-15
 198
198
 2024-04-14
2024-04-14
 193
193
 2024-04-13
2024-04-13
 202
202
 2024-04-13
2024-04-13
 190
190
 2024-04-13
2024-04-13
 197
197
 2024-04-13
2024-04-13
 176
176
 2024-04-13
2024-04-13
 199
199
 2024-04-11
2024-04-11
 187
187
 2024-04-11
2024-04-11
 201
201
 2024-04-11
2024-04-11
 186
186
 2024-04-11
2024-04-11
 187
187
 2024-04-11
2024-04-11
 184
184
 2024-04-09
2024-04-09
 179
179
 2024-04-09
2024-04-09
 167
167
 2024-04-09
2024-04-09
 191
191
 2024-04-09
2024-04-09
 198
198
Create your
podcast in
minutes
- Full-featured podcast site
- Unlimited storage and bandwidth
- Comprehensive podcast stats
- Distribute to Apple Podcasts, Spotify, and more
- Make money with your podcast
It is Free
- Privacy Policy
- Cookie Policy
- Terms of Use
- Consent Preferences
- Copyright © 2015-2024 Podbean.com