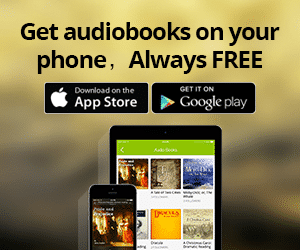ひたすら祈りに精進し続けるうちに、結婚する時が来たことを直感しました。神の道を行くと決めた以上、すべての歩みは神の支配下にあります。祈りを通して時を知れば従わざるを得ませんでした。そこで、仲人の経験豊富なある婦人に依頼して、定州の有名なキリスト教家庭の娘である崔先吉と見合いをしたのち、略式の婚約をしました。
彼女はとても由緒ある家庭で生まれ育った真心を尽くす女性でした。小学校しか出ていませんでしたが、ほんのわずかでも人の世話にはならないという性格で、神社参拝を拒否して十五歳で獄中生活をしたほど、信念のある信仰深い女性でした。私は二十四番目の新郎候補だったそうで、彼女は新郎を選びに選んだのです。しかしながら、ソウルに戻った私は、見合いをしたことさえ忘れてしまうほど切迫した心情にありました。
私はもともと、留学から戻ったら、中国、ソ連、モンゴルの国境都市である中国の海拉爾に行く計画でした。満州電業株式会社に就職して三年ほど生活しながら、中国語とロシア語、モンゴル語を学ぼうと考えていました。日本に打ち勝つために日本語を教える学校に通ったように、来るべき未来に備えようと、三国の国境地域に行って外国語をいくつか学ぶつもりでした。ところが、当時、情勢が尋常ではありませんでした。どうしても満州に行ってはならないようで、就職予定を取り消しに満州電業安東支店(安東は鴨緑江の対岸にある現在の中国・丹東)に行きました。そこで手続きを終えた後、故郷の定州に戻ってみると、お見合いを準備してくれた婦人が大騒ぎを起こしていました。婚約した女性が私でなければ嫁に行かないと言い張って大変だと言うのです。私を見るやいなや女性の家に連れて行きました。
私は彼女に、これから私がどう生きていくかをはっきりと話しました。
「いま結婚しても、少なくとも七年ほどは、あなた一人で生きる覚悟をしなければならない」
「なぜそうしなければならないのですか」
「私には結婚生活よりもっと重要なことがある。実際、結婚するのも神様の摂理を遂行するためだ。私たちの結婚は、家庭を超えて、民族と人類を愛することのできる位置まで行かなければならない。私の意志がこうであっても、心から私と結婚したいのか」
すると女性は、「好きなようにしていいです。あなたに会った後、月の光の中で花が満開になっている夢を見たので、あなたは問違いなく天が私に下さった連れ合いです。ですから、どのような困難があっても我慢できます」と、気丈な態度で答えました。それでもまだ不安だった私は、何度か彼女の固い誓いを確認し、そのたびに彼女は「あなたと結婚できさえすれば、どんな事情があっても尽くすので、何の心配もしないでください」と答えて、私を安心させました。
四月に結婚式を挙げる予定が、義父が急に亡くなったので、当初の日取りを延期して一九四四年五月四日に婚礼を行いました。五月は普通ならのどかな春の日ですが、その日は土砂降りの雨でした。イエス教の李浩彬牧師が主礼を務めてくれました。李浩彬牧師は光復(日本の敗戦で植民統治から解放されたこと。一九四五年八月十五日を指す)後、南に下って超教派的な中央神学院を設立した人です。
自炊していたソウルの黒石洞で新婚生活を始めました。「まあ、まるで卵を扱っているみたいで、どれだけ美しいお嫁さんなのかしら」と言った下宿屋のおばさんの言葉どおり、私は妻を心から大事にし、愛しました。
当時の私は、龍山にある土木会社の鹿島組京城営業所に就職して、会社の仕事と教会の仕事を一緒にしていました。ところがその年の十月、新婚の家に突然日本の警察がやって来て、「早稲田大学の経済学部に通っていた誰それを知っているか」と尋ねるなり、答えも待たずに私を京畿道警察部に連行しました。共産主義者として引っ張られていった友人の口から、私の名前が出たことが理由でした。
警察に連行された私は、いきなり拷問を受けました。
「おまえも共産党だろう?内地に留学して、そいつと同じ仕事をしただろう?おまえがいくら違うと意地を張っても無駄だ。警視庁に照会すれば分かるようになっている。こんな所で犬死にしないように、共産党の奴らの名前を全部吐くことだな」
日本で同じ活動をしていた友人の名前を吐けと言って、机の脚に使う角材が四本とも壊れるほど殴られましたが、私は最後まで話しませんでした。
すると、次に警察は、黒石洞の新婚の家を家捜しして日記帳を押収しました。彼らは日記帳を一枚一枚めくっていって、友人の名前を突き止めようとしましたが、私は死を覚悟して知らないと突っぱねました。
戦争は終わりの時が近づき、焦りの色を濃くした日本の警察の拷問は、とても言葉で言い表せないほど残酷でした。彼らは鋲を打った軍靴で私の体を容赦なく踏みつけ、私が死んだようにぐったりすると、天井に吊して揺らしました。精肉店の肉塊と化した私の体は、彼らが押す棒に任せてあちこち揺れ動き、口からは鮮血がほとばしってセメントの床を濡らしました。何度も気を失い、そのたびにバケツ一杯の冷水をかけられ、意識が戻ればまた拷問です。鼻をつまんで、洋銀製のやかんを口の中に突っ込み、大量の水を無理やり飲ませる拷問もありました。床に倒れた後、カエルのように膨れ上がったおなかを軍靴で踏みつけます。食道を通って上がってきた水を吐き出すと、目の前が真っ暗になって何も見えませんでした。そんな拷問を受けた日は、食道が燃えるように痛み、水っぽい汁でさえ一口も喉を通らず、剥き出しの床に力なく俯になって、ぴくりとも動けませんでした。
私はついに友人の名を口にせず、拷問を耐え抜きました。意識が朦朧となる中でも、それだけは死に物狂いで守り通しました。ところが、業を煮やした警察は、故郷の母親を呼ぶ作戦に出たのです。足が伸びきって思うように立つこともできなかった私は、複数の警官に両腕を挟まれて、面会室まで辛うじて歩いて行きました。母は私に会う前から、もう目の周りが涙でただれていました。血まみれになった息子の顔を見て、
「少しだけ我慢しなさい。自分が何としてでも弁護士をつけてあげるから。その時までどうか死なずに耐え忍んでほしい」
と必死に訴える母でした。しかし、「いくら志が良くても、おまえの命を守るほうが先だ。絶対に死んではならない」と言って泣いている母を眺める私の心は、つらく切ないものでした。心の中では、「お母さん1」と言って共に抱き合い、こんこんと泣きたい気持ちでした。けれども、母親に面会させる警察の意図をよく知る私としては、そうはできなかったのです。母の言葉に私ができる返事と言えば、裂けてぶくぶくと膨れた目をしきりに瞬きさせることだけでした。
京畿道警察部に拘束された四カ月間、下宿屋の李奇鳳おばさんとその姉妹たちが交代で差し入れをしてくれました。おばさんは面会するたびに泣くので、私は「少しだけ我慢すれば、この時代は間もなく終わります。遠からず日本は滅びますから、泣かないでください」とおばさんを慰めました。それは自分の言葉ではなく、神様が私に下さった信仰でした。
翌一九四五年二月、警察から解放されて出て来るとすぐ、私は下宿の日記帳をひとまとめにして、漢江の川辺に行きました。そして、もうこれ以上友人に被害が及ばないように、そのたくさんの日記帳をことごとく焼き捨てました。そのまま残しておけば、私が監獄に入るたびに禍根になるかもしれないものでした。
拷問でぼろぼろになった体はなかなか回復しませんでした。長い間血便が出て、体を動かせずに難儀する私を、下宿屋のおばさんの姉妹たちが真心を込めて世話してくれました。
ついに一九四五年八月十五日、待ちに待った光復の日が来ました。三千里半島 (朝鮮半島の南北の長さを三千朝鮮里とした伝統的表現) が「万歳!」の声と太極旗の渦に覆われた感激の日でした。しかし私は、遠からず朝鮮半島に訪れるであろう驚くべき災難を予感して、とても深刻になり、喜んで万歳を叫ぶことができませんでした。独り小さな部屋に閉じこもって、祈りに熱中しました。不吉な予感どおり、祖国は日本の植民地支配から解放されましたが、すぐに三八度線で国が二つに分かれました。北朝鮮の地に、神の存在を否定する共産党が足を踏み入れたのです。
More Episodes
 2023-08-08
2023-08-08
 194
194
 2023-08-08
2023-08-08
 178
178
 2023-08-08
2023-08-08
 199
199
 2023-08-08
2023-08-08
 195
195
 2023-08-08
2023-08-08
 194
194
 2023-08-07
2023-08-07
 210
210
 2023-08-06
2023-08-06
 215
215
 2023-08-06
2023-08-06
 214
214
 2023-08-06
2023-08-06
 192
192
 2023-08-06
2023-08-06
 190
190
 2023-08-06
2023-08-06
 201
201
 2023-08-06
2023-08-06
 216
216
 2023-08-06
2023-08-06
 199
199
 2023-08-06
2023-08-06
 206
206
 2023-08-01
2023-08-01
 202
202
 2023-08-01
2023-08-01
 202
202
 2023-08-01
2023-08-01
 205
205
 2023-08-01
2023-08-01
 192
192
 2023-08-01
2023-08-01
 25
25
 2023-07-29
2023-07-29
 221
221
Create your
podcast in
minutes
- Full-featured podcast site
- Unlimited storage and bandwidth
- Comprehensive podcast stats
- Distribute to Apple Podcasts, Spotify, and more
- Make money with your podcast
It is Free
- Privacy Policy
- Cookie Policy
- Terms of Use
- Consent Preferences
- Copyright © 2015-2024 Podbean.com