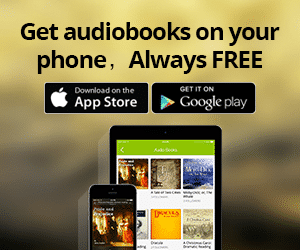ゴルバチョフ大統領との会談を終えてクレムリン宮殿を出てくる際、私は随行していた朴普熙(当時、ワシントン・タイムズ社長)に特別な指示を一つしました。
「1991年を越える前に金日成主席と会わなければならない。時間がない! ソ連はもう一、二年のうちに終わってしまう。問題は韓国だ。何としてでも金日成主席と会い、朝鮮半島で戦争が起きるのを防がなければならない」
ソ連が崩壊すれば全世界の共産国家も一緒に壊滅するので、急いでいました。そうなれば、窮地に追い込まれた北朝鮮がどのような挑発をしてくるか分かりません。その上、北朝鮮は核兵器に強く執着していたので、なおさら不安でした。北朝鮮との戦争を防ごうとすれば、北朝鮮と話ができるチャンネルがなければならなかったのですが、その時まで私たちにはそのようなものがありませんでした。何が何でも金日成主席と会い、核兵器に対する野望を捨てさせ、韓国を先制攻撃しないという約束を取り付けなければなりませんでした。
朝鮮半島は世界情勢の縮図です。朝鮮半島で血を流せば世界が血を流します。朝鮮半島が和解すれば世界が和解し、朝鮮半島が統一されれば世界が統一されるのです。ところが、1980年代後半から、北朝鮮は核保有国家になろうとあがいていました。これに対して欧米諸国は、先制攻撃をすると高飛車な態度で脅していました。このまま極限まで突き進めば、北朝鮮がどんな強硬手段を講じるか分かりませんでした。私は、どうしても北朝鮮との対話のチャンネルを構築しなければならないと考えたのです。
しかし、事はそう簡単ではありませんでした。北朝鮮と接触していた朴普熙に対して、北朝鮮政府の金達鉉副総理は、「北朝鮮の人民は、今まで文総裁を国際的な勝共運動の魁首と思ってきました。それなのに、どうして保守・反共の総帥を歓迎できますか。これは到底想像外のことに思えます」と強く釘を刺してきたのです。しかし、朴普熙はあきらめませんでした。
「アメリカのニクソン大統領は徹底した保守・反共主義者です。その彼が中国を訪問して、毛沢東主席と会談を行い、米中の国交が正常化しました。ここから利得を得たのは中国です。侵略者の烙印を押されていた中国が、一躍世界舞台の表面に浮き上がってきたのです。北朝鮮が国際社会で信用を得ようとすれば、文総裁のような保守・反共主義者を友人にしなければなりません」
と北朝鮮を説得しました。
1991年11月30日、ついに金日成主席が私たち夫婦を北朝鮮に招待しました。当時、ハワイに滞在していた私たちは、急遽、北京に飛びました。中国政府が用意した北京空港の貴賓室でしばらく待っていると、北朝鮮の代表が現れ、正式招待状を出してきました。
招待状には、平壌の官印が鮮明に押されていました。
「朝鮮民主主義人民共和国は、統一教会の教主・文鮮明と令夫人、そして随行員一同を共和国に招請します。共和国は在北期間中、その身元を保証いたします。
1991年11月30日
朝鮮民主主義人民共和国政務院副総理 金達鉉」
私たち一行は、金日成主席が用意した朝鮮民航特別機IS215に乗って平壌に向かいました。これは、極めて異例で、特別な待遇でした。
特別機は黄海を渡って新義州方面に向かい、そこから故郷の定州上空を通過して平壌に行きました。故郷が目に入るように配慮してくれたのですが、夕焼けに赤く染まった故郷の山河を見下ろすと、胸が高鳴って心の奥底がしびれるようでした。あれが本当に私の故郷なのかと思うと、すぐにでも飛び降りて山や野原を走ってみたいと思いました。
平壌の順安空港には、46年前に別れた家族が出てきていました。花のように美しかった妹は初老のお婆さんになり、私の手を握って顔をしわくちゃにして泣きました。70歳を超えた姉も、私の肩をつかんで激しく泣き、涙を流しましたが、私は最後まで泣きませんでした。
「ここでそのようにしないでください。家族に会うことも大切ですが、私は神様の仕事をするために来たのです。そのようにしないで、気持ちをしっかり持ってください」
四十数年ぶりに出会った姉妹たちを抱きかかえて泣くことができない私の心の中では、涙が滝のように流れていました。しかし、私は何とか心を抑えて宿所に向かいました。
翌日、いつものとおり早朝に起きて祈りました。もし迎賓館に監視設備があったなら、朝鮮半島の統一のために泣く私の祈りがすべて記録されているでしょう。その日私たちは、平壌市内を回りました。平壌は主体思想の赤い標語で完全に武装されていました。
4日目は、特別機に乗って金剛山の名勝地を隅々まで見て回った後、6日目は、ヘリコプターに乗って故郷に行きました。夢の中でも慕わしくて一足飛びに駆け寄ったその家が、いま目の前に現れました。夢か現かと思って、しばらく家の前で望夫石(中国湖北武昌の北の山にある岩。昔、貞女が戦争に出かける夫をこの山で見送り、そのまま岩になったと伝えられている)のように立った後、家の中に入っていきました。本来は、母屋と倉庫、離れと家畜小屋が互いに向かい合った四角形の家でしたが、今は母屋だけが残っていました。私が生まれた奥の間に入っていき、あぐらをかいて座ってみました。このようなとき、昔の記憶がきのうのことのように鮮明に蘇ります。奥の小さな扉を開いて奥庭を見てみると、昔、私が登って遊んでいた栗の木は、すでに切られてなくなっていました。「うちの小さな目、おなかは空いていないのか?」と母が私を優しく呼ぶようでした。母の木綿のチマ(スカート)がさっと私の目の前を通り過ぎていきました。
故郷で両親の墓を訪ねて花を捧げました。興南の監獄に私を訪ねてきて悲しみの涙を流した母の姿が、私が母を見た最後でした。母の墓の上を昨晩降った雪が軽く覆っていました。私は白い雪を手の平で払い、母の墓に生えた芝をしばらく撫でました。母の荒れた手の甲のように、墓の上の冬の芝はざらざらしていました。
More Episodes
 2024-10-13
2024-10-13
 143
143
 2024-10-13
2024-10-13
 136
136
 2024-10-13
2024-10-13
 134
134
 2024-10-10
2024-10-10
 145
145
 2024-10-10
2024-10-10
 141
141
 2024-10-10
2024-10-10
 136
136
 2024-10-10
2024-10-10
 125
125
 2024-10-04
2024-10-04
 155
155
 2024-10-04
2024-10-04
 141
141
 2024-10-04
2024-10-04
 143
143
 2024-10-04
2024-10-04
 141
141
 2024-10-04
2024-10-04
 146
146
 2024-10-02
2024-10-02
 141
141
 2024-09-27
2024-09-27
 145
145
 2024-09-27
2024-09-27
 159
159
 2024-09-27
2024-09-27
 155
155
 2024-09-27
2024-09-27
 141
141
 2024-09-27
2024-09-27
 144
144
 2024-09-22
2024-09-22
 159
159
 2024-09-19
2024-09-19
 150
150
Create your
podcast in
minutes
- Full-featured podcast site
- Unlimited storage and bandwidth
- Comprehensive podcast stats
- Distribute to Apple Podcasts, Spotify, and more
- Make money with your podcast
It is Free
- Privacy Policy
- Cookie Policy
- Terms of Use
- Consent Preferences
- Copyright © 2015-2024 Podbean.com